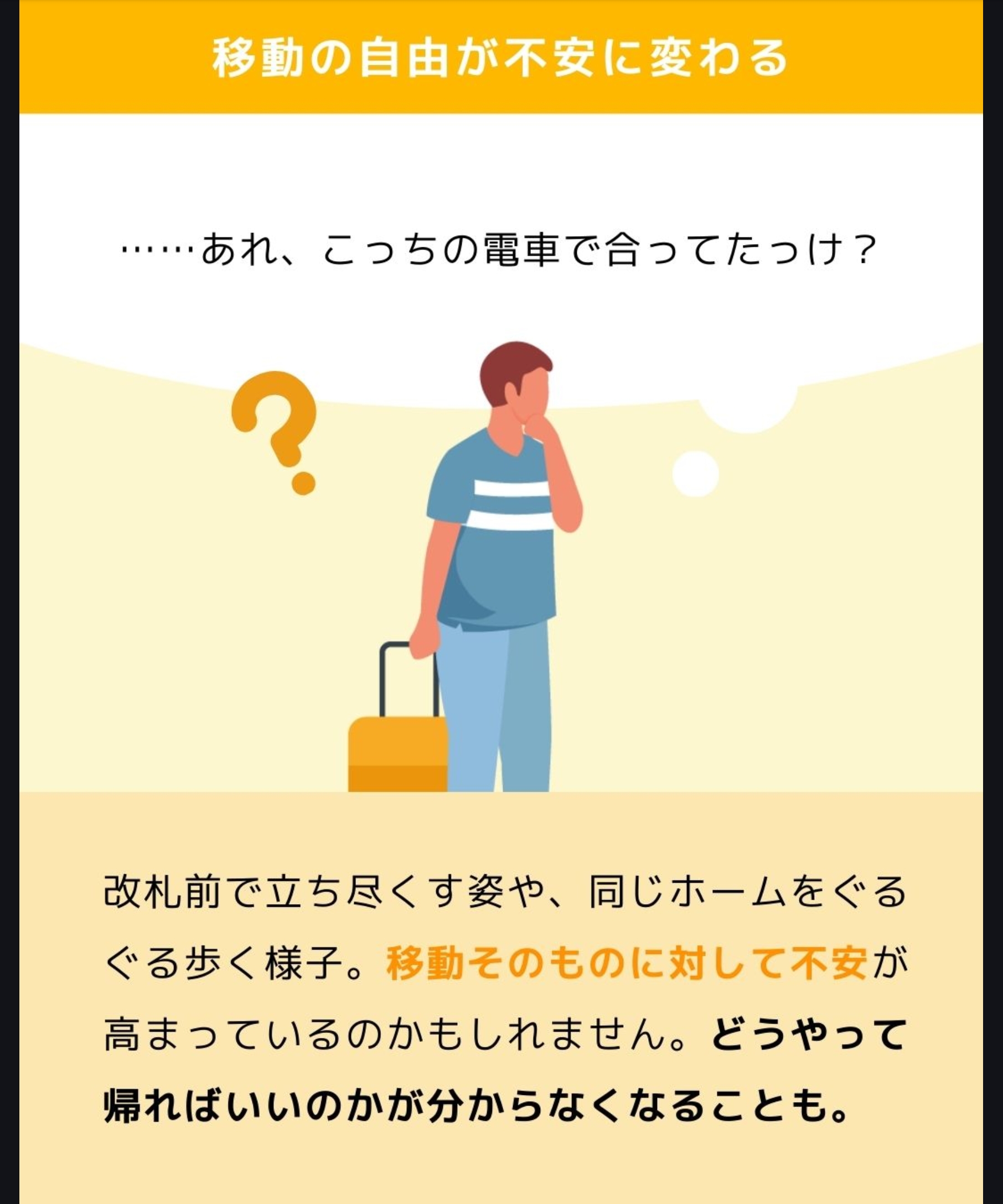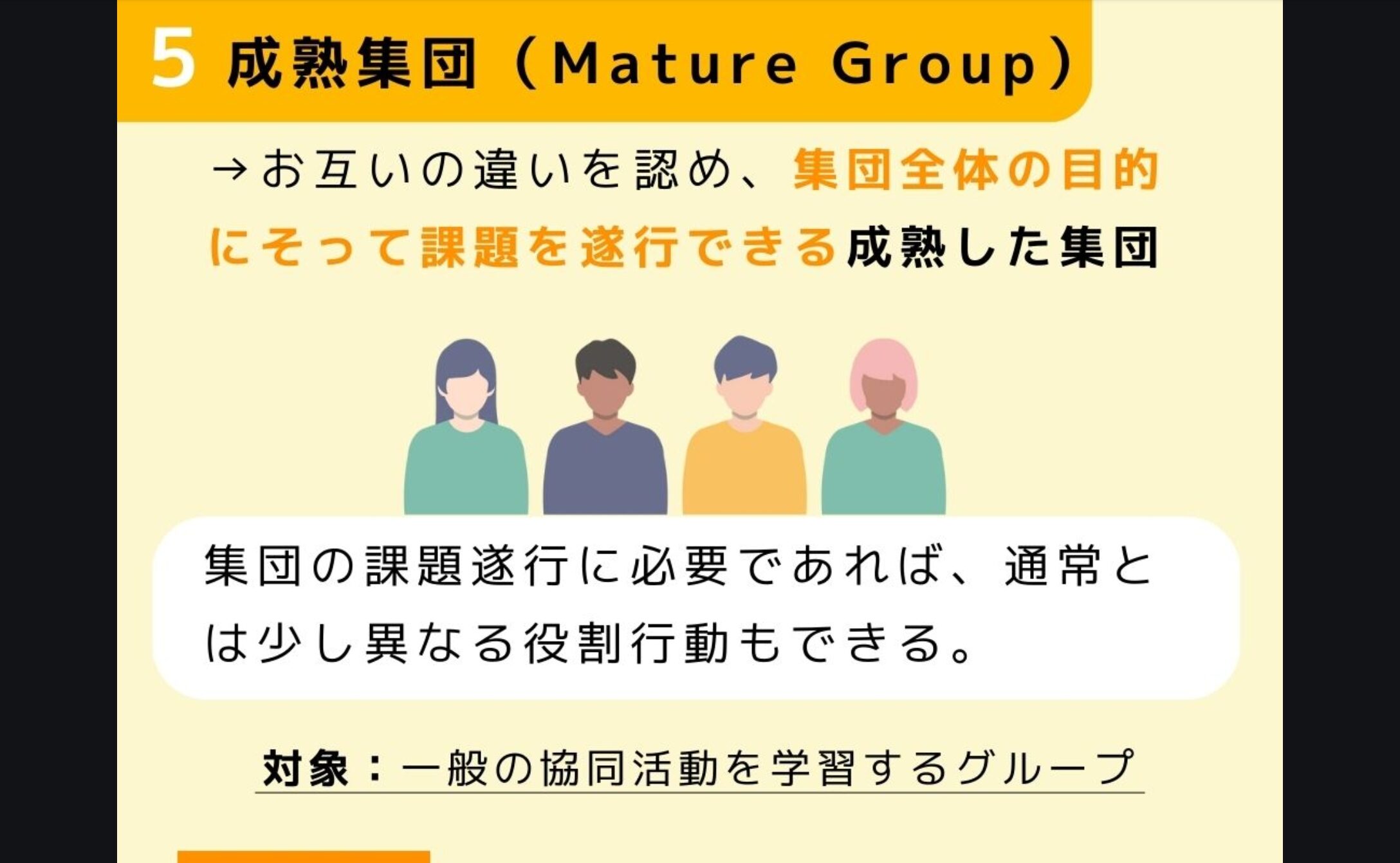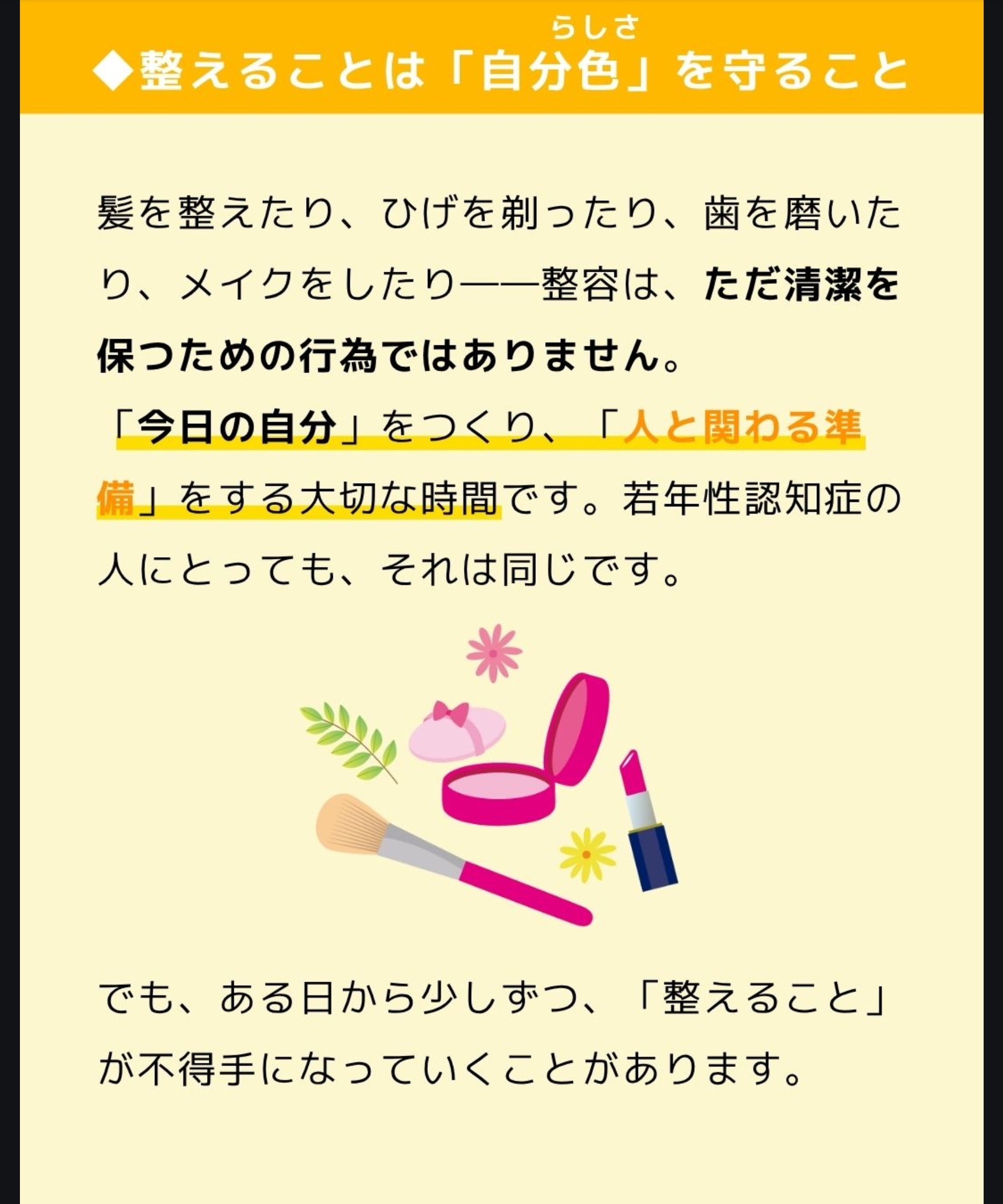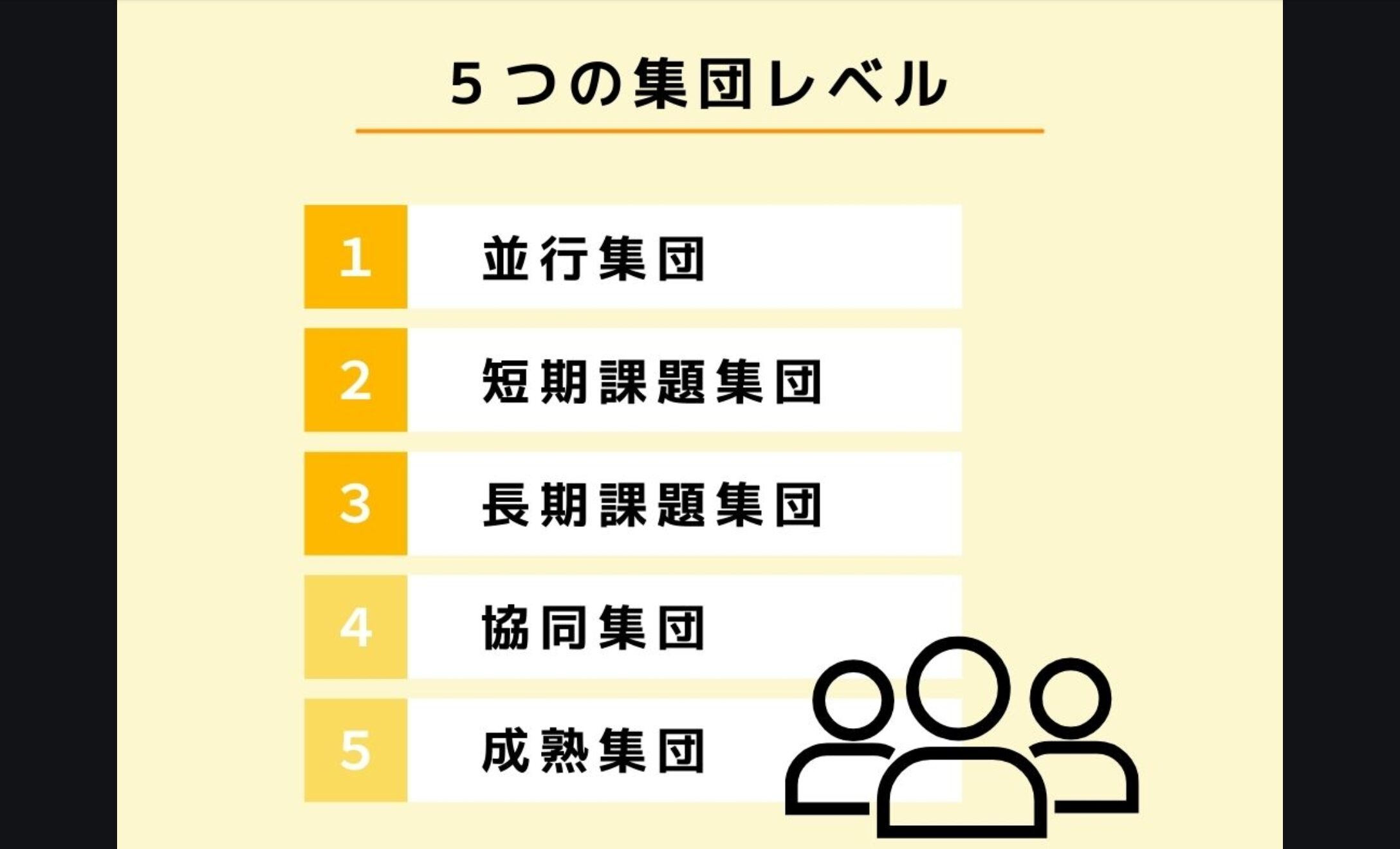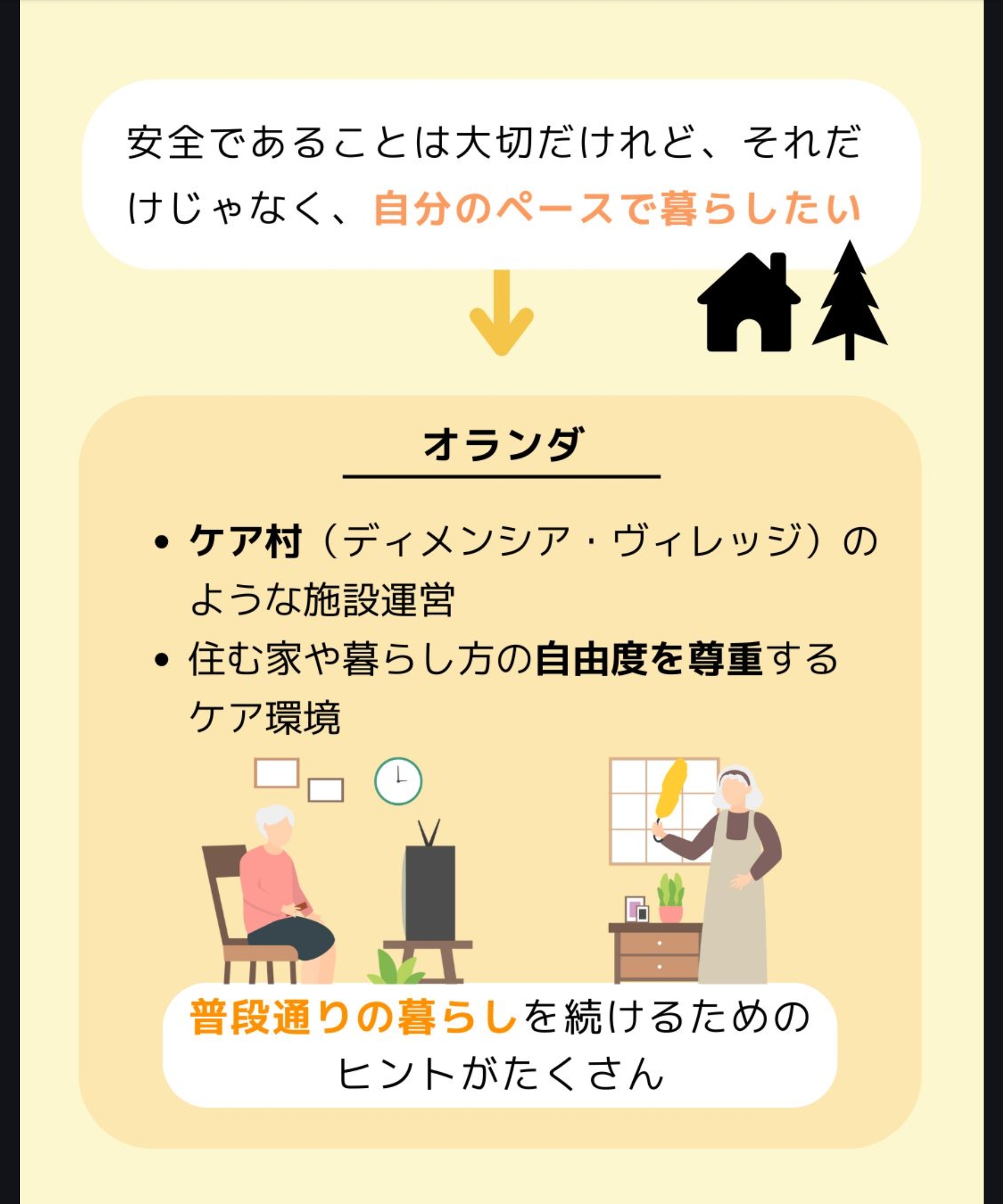『診断までの道のり―「気づき」は 誰のものか どこに生まれるのかー』
弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。
パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝です!
こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)
前回からは、原点回帰を大切に「若年性認知症」について新たに考え、これまでとは異なる視点で解説していますが・・・・・今回はこちらです。
診断までの道のり
―「気づき」は 誰のものか どこに生まれるのか―
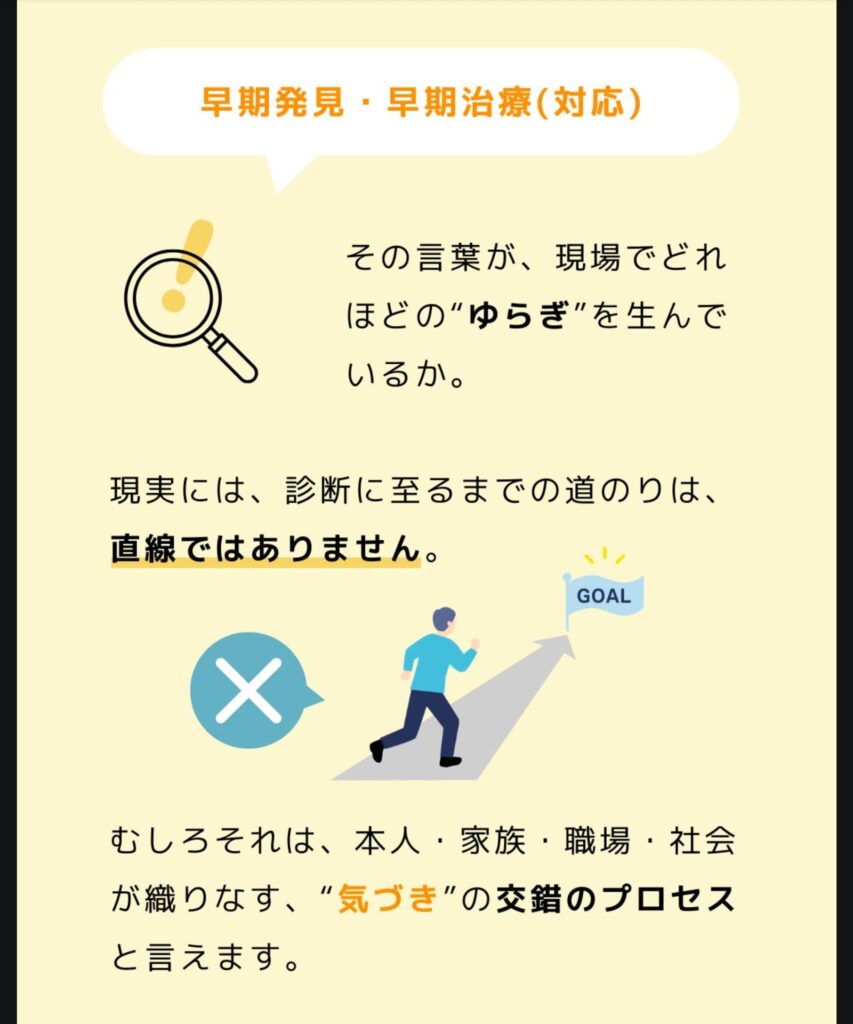
「早期発見・早期治療(対応)」
その言葉が、現場でどれほどの“ゆらぎ”を生んでいるか。
現実には、診断に至るまでの道のりは、直線ではありません。
むしろそれは、本人・家族・職場・社会が織りなす、“気づき”の交錯のプロセスといえます。
【1】“物忘れ”が最初に見えても、それは“表面”にすぎない
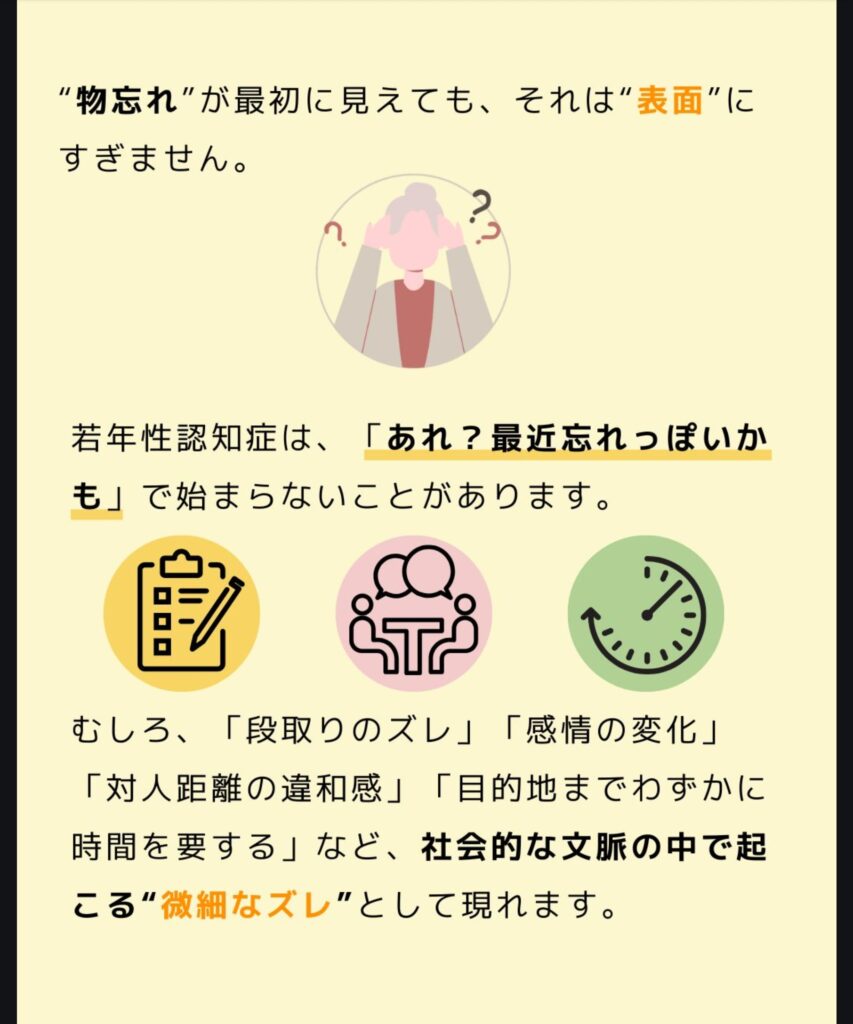
- 若年性認知症は、「あれ?最近忘れっぽいかも」で始まらないことがある。
むしろ、「段取りのズレ」「感情の変化」「対人距離の違和感」「目的地までわずかに時間を要する」など、**社会的な文脈の中で起こる“微細なズレ”**として現れる。 - たとえば・・・・・
◆社会の中で見えてくるズレ(人間関係・対人距離・地域との関わり)
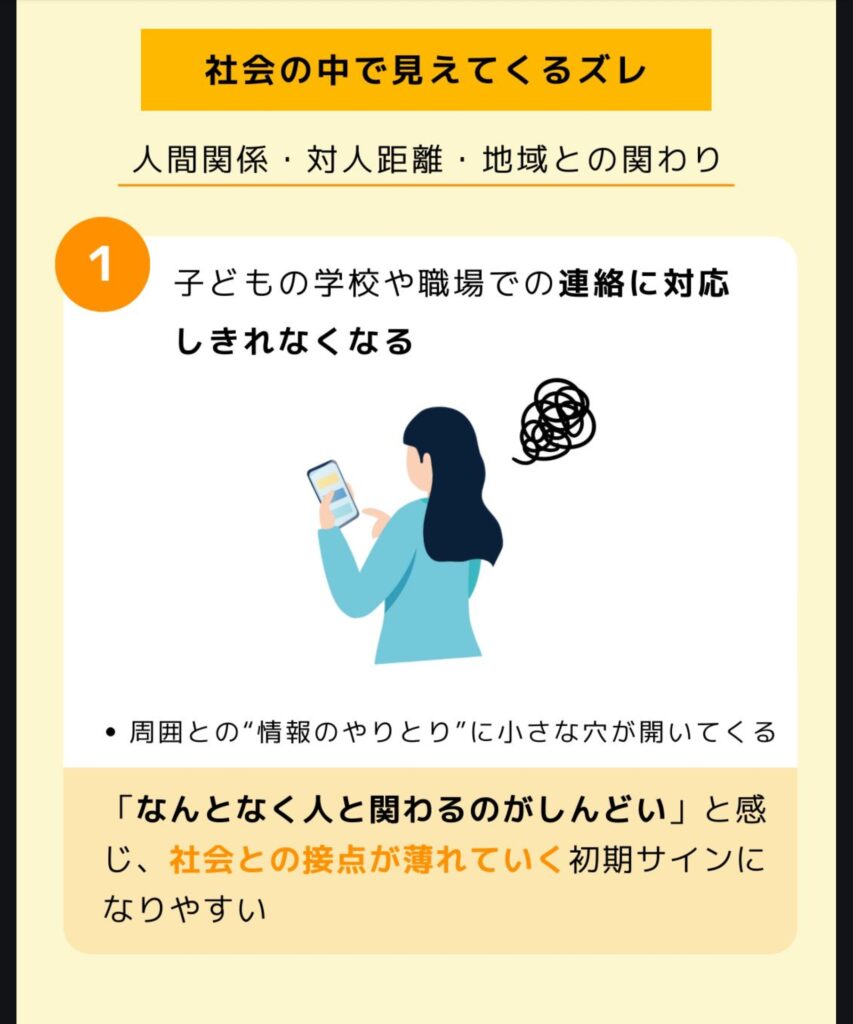
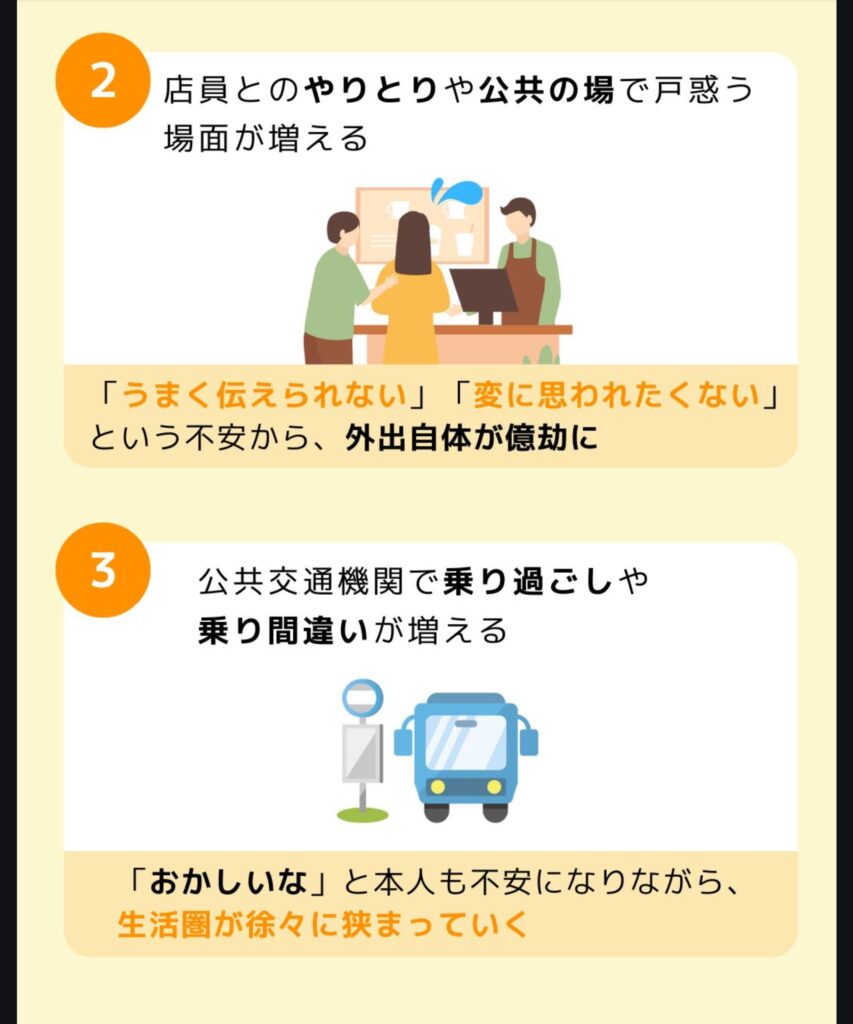
1.子どもの学校や職場での連絡に対応しきれなくなる
→ 学校からの配布物や連絡帳の確認を忘れる、保護者会の時間を勘違いする、会社のLINEやメールでの連絡に返事が遅れる・漏れるなど、周囲との“情報のやりとり”に小さな穴が開いてくる。
「なんとなく人と関わるのがしんどい」と感じ、社会との接点が薄れていく初期サインになりやすい。
2. 店員とのやりとりや公共の場で戸惑う場面が増える
→ レジで財布を出すのに時間がかかったり、注文をうまく伝えられず言葉がつまる。
**「うまく伝えられない」「変に思われたくない」**という不安から、外出自体が億劫になることもある。
3. 公共交通機関で乗り過ごしや乗り間違いが増える
→ 慣れているはずの路線で迷ったり、下車駅をうっかり通り過ぎてしまう。
「おかしいな」と本人も不安になりながら、生活圏が徐々に狭まっていく。
それらは、本人の“疲労”や“性格の問題”にすり替えられやすい。
「違和感」には気づけても、「それが認知症かもしれない」とは思いにくい構造がある。
◆仕事の中で見えてくるズレ(職場のパフォーマンスや信頼関係)
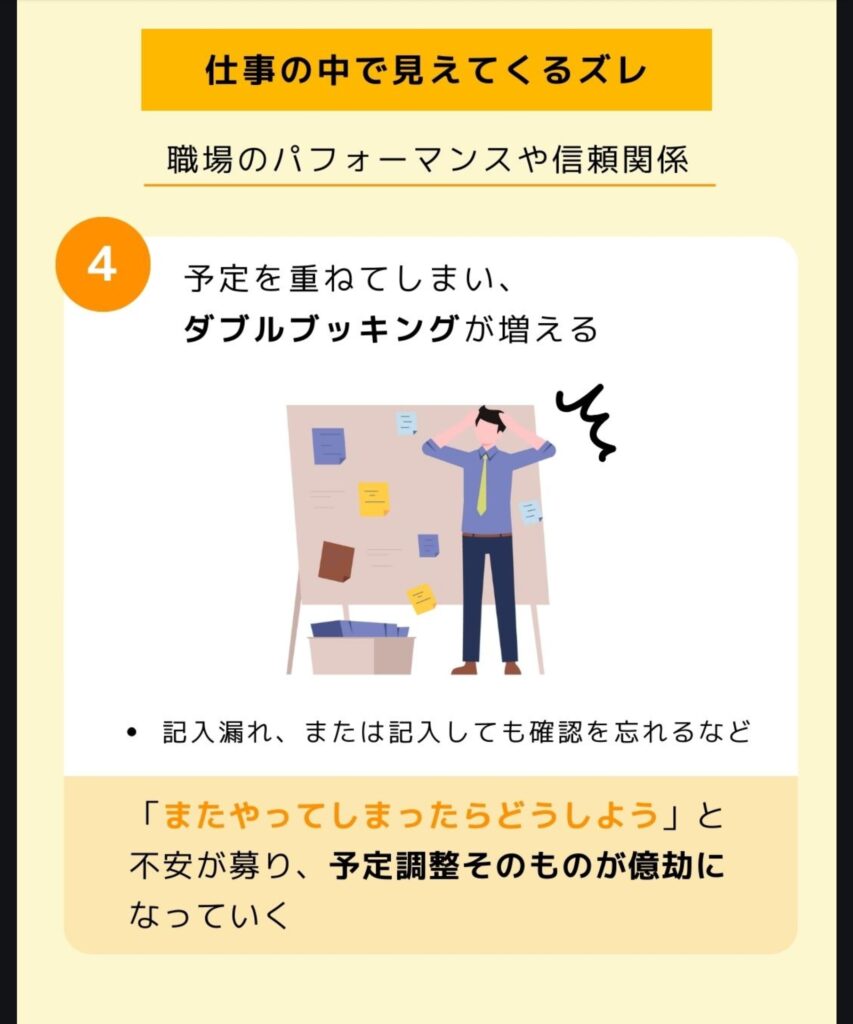
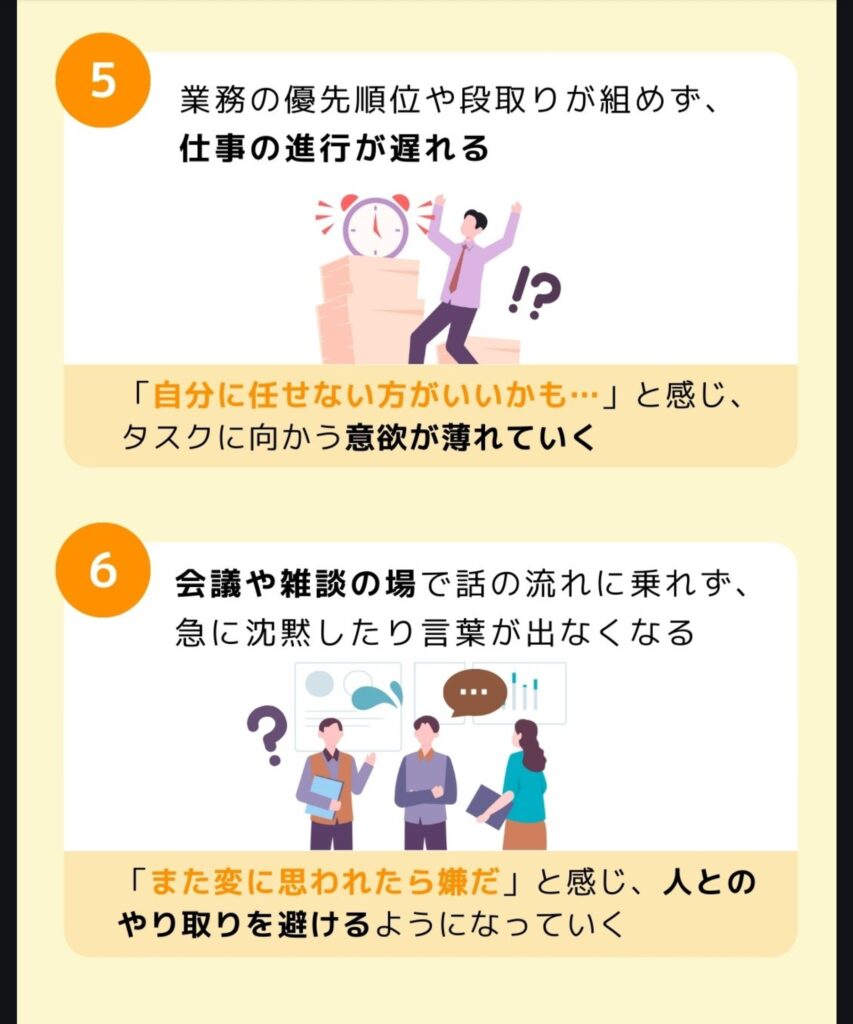
4. 予定を重ねてしまい、ダブルブッキングが増える
→ 手帳にメモしていたのに記入漏れ、または記入しても確認を忘れる。
「またやってしまったらどうしよう」と不安が募り、予定調整そのものが億劫になっていく。
5. 業務の優先順位や段取りが組めず、仕事の進行が遅れる
→ ミスではなく「進まない」ことが増え、周囲がフォローに入ることが増える。
「自分に任せない方がいいかも…」と感じ、タスクに向かう意欲が薄れていく。
6. 会議や雑談の場で話の流れに乗れず、急に沈黙したり言葉が出なくなる
→ 話す力ではなく、“会話の流れをつかむ力”が落ちてきている。
「また変に思われたら嫌だ」と感じ、人とのやり取りを避けるようになっていく。
◆生活の中で見えてくるズレ(家庭や日常動作・役割の変化)
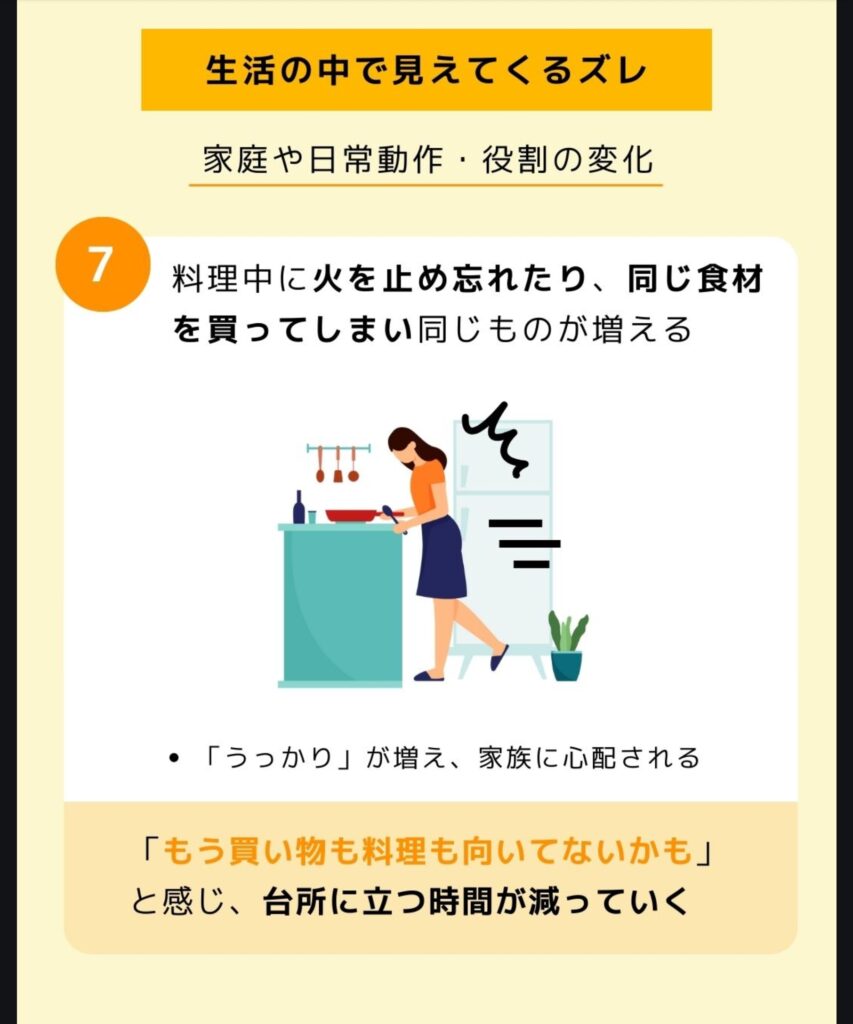
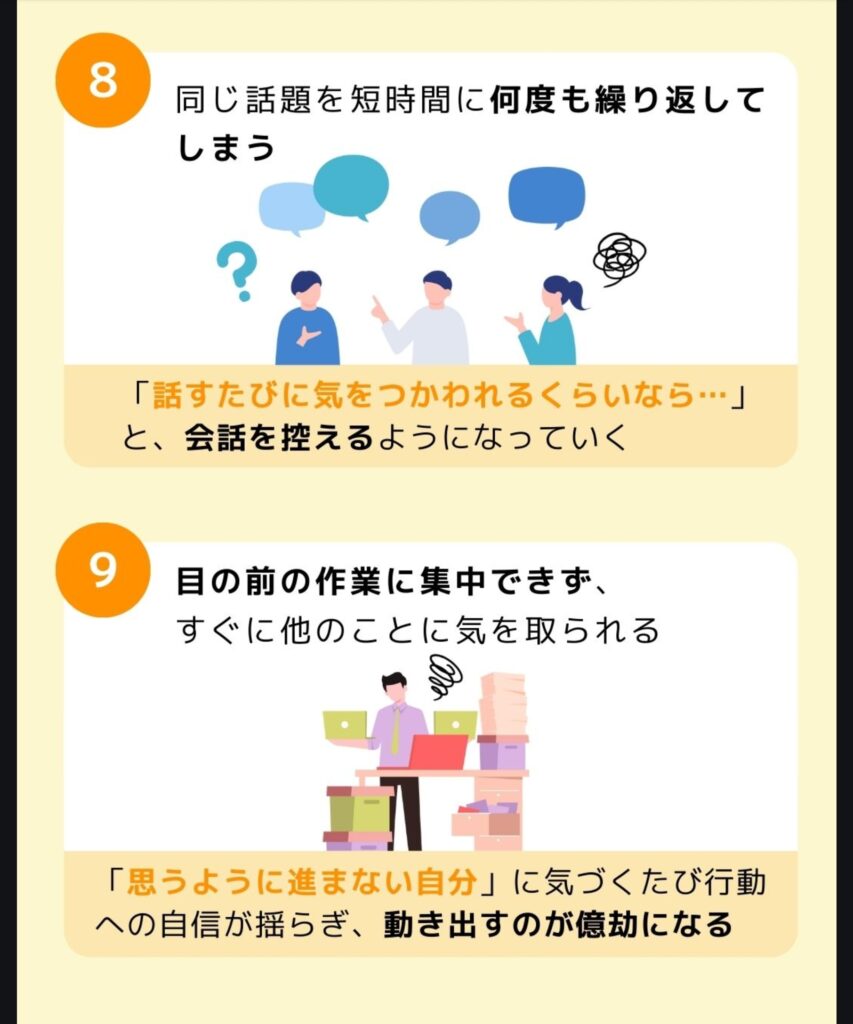
7. 料理中に火を止め忘れたり、同じ食材を買ってしまい同じものが増える
→ 「うっかり」が増え、家族に「大丈夫?」と心配される。ドレッシングばかりが増えていく。
「もう買い物も料理も向いてないかも」と感じ、台所に立つ時間が減っていく。
8. 同じ話題を短時間に何度も繰り返してしまう
→ 本人は自然な会話のつもりでも、周囲は「何かおかしい?」と感じ始める。
「話すたびに気をつかわれるくらいなら…」と、会話を控えるようになっていく。
9. 目の前の作業に集中できず、すぐに他のことに気を取られる
→ 以前はテキパキ動けていた人が、「あれ、何してたっけ?」が増えてくる。
「思うように進まない自分」に気づくたび、行動への自信が揺らぎ、動き出すのが億劫になる。
次回は、気づきの主体について、診断「告げる」、「行動する」などについて解説していきます。
「診断までの道のり―「気づき」は、誰のものか。どこに生まれるのか」について、こんな考え方が他にもあります、私が聞いた話はこのようなものでした、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪